異界からの呼び声
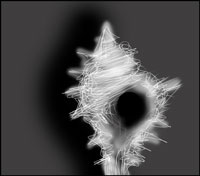 異界からの呼び声
異界からの呼び声
ミショーの詩を読んでギョッとした。短いプロットをつないで描かれた内容から察するに、夫人は凄惨な死を遂げていたのだ。どうしてそんなことに?
アンリ・ミショー(1899-1984)ベルギー生まれのフランスの詩人。医師の指導下、実験的にメスカリン(麻薬)による精神の極北を旅した風景を描いた画家でもある。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
読んでいると、胃がキリキリするようなミショーの作風。その感性が巡り合った妻。凄みの詩神は、凄惨な死を愛したのだろうか?
メシアンの伴侶だった女性も、出産後に発狂している。異界に触れてしまった詩人、音楽家は、やはり異界からの呼び声を聴き続けるのか?
オリビエ・メシアン(1908-1992)フランスの作曲家。鳥類学者でもあり、鳥の鳴き声をモチーフにしたピアノ曲「鳥のカタログ」がある。動画・愛の部屋の音楽は2つのピアノのための「アーメンの幻影」から編集した。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
ミショー夫人の焼死。燔祭の生贄? 何のための犠牲だったというのか? 病院のベッドの上でひと月の間、包帯でミイラのようになったのち、血液異常で他界するとは。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
「火が私の家の上に黒い布を広げた」と、ミショーは詩っている。暖炉の火が彼女の衣服に燃え移ったときから、耐えなければならない時間が始まったのだ。治癒への希望を持って、緩慢な死へ向かって。
傍らにいる人間は、見守ることしかすべがない。そうして深く降りて行くのだ。異界へと。
異界は、ふと隣室へ行くような、あるいはエレベーターで二階へ上がるような、また雨のように降り注いでくるような、形なき神出鬼没な在り処。訪うとしても辿り着けず、かと思えばそこにいて、いると思ったら、もういない。そんな風に異界は、いつも私たちの傍にある。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
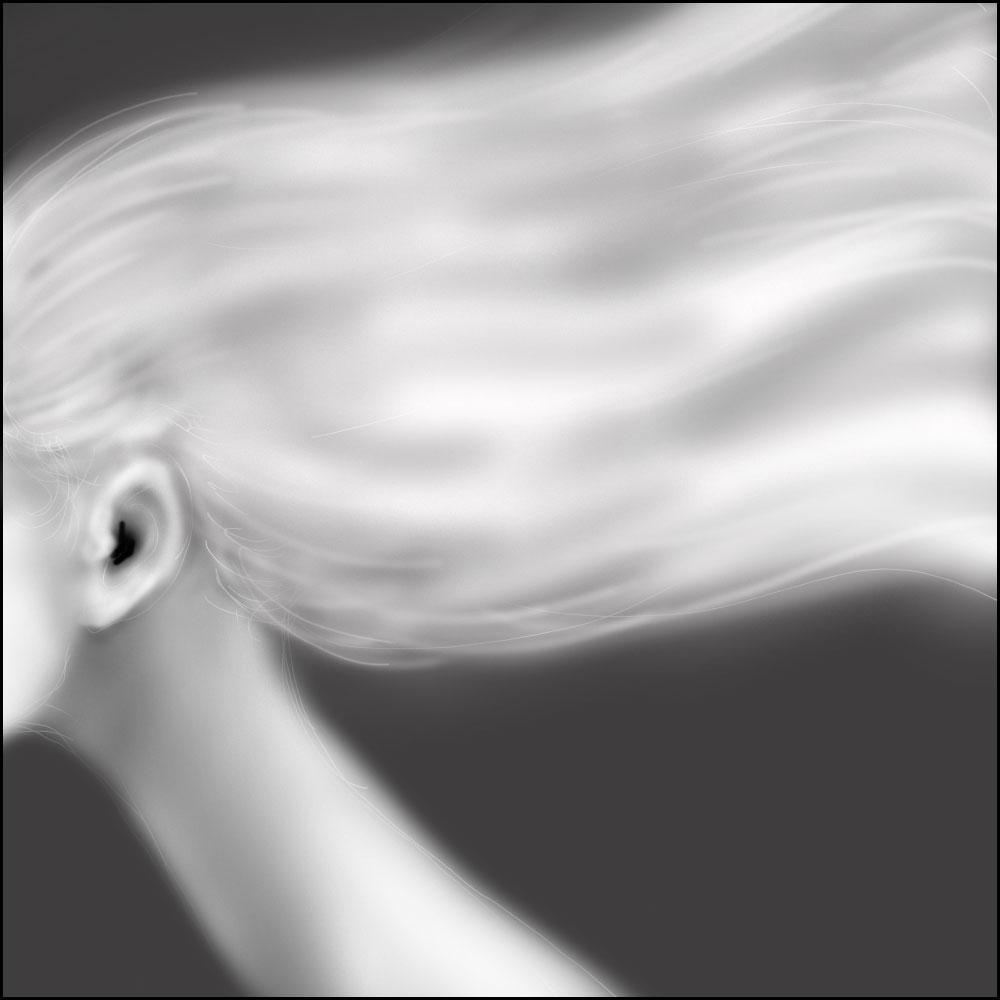
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
人が最初に異界へ行く切符を手にするのは、近親者の死、自分の臨死、いかんせん死が傍らを通る時、その切符を分配する。そして異界は、泡立つ血の池で溺れるような、巨石を背負って歩かなければならないような地獄ではない。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
最初に見るのは、息を引き取った人の足跡であり、かの人たちの、肉体という器から解放された喜びだろう。魂がそこから出てそこへ帰るところ。人が人の死に立ち会うのは、その場所を知るためではなかったか?
死を迎えた人たちは、今や魂となって「私はここで生きています」と、言葉なき言葉で告げている。言葉なき言葉を聞く耳こそ、直観なのだ。
あの人は、あの世で生きている。これが異界からの呼び声を聴いた者たちの、率直な言い分だ。そんなこと信じられない? だからミショー氏も、最後の行で遠慮がちにこう結んでいる。「われら今も二人」と。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆







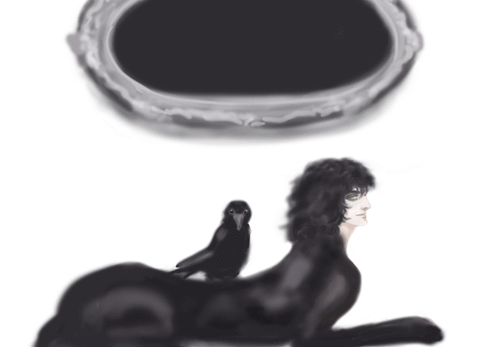
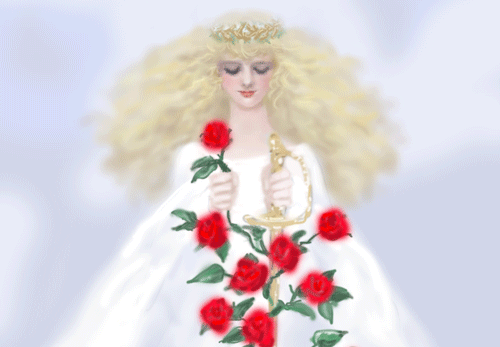
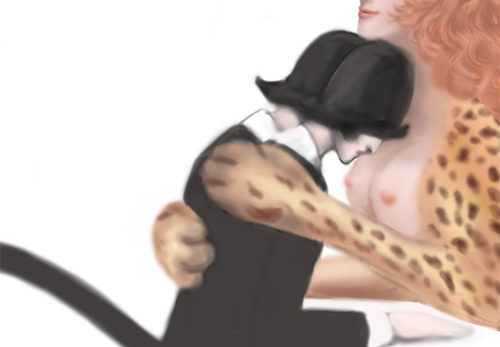


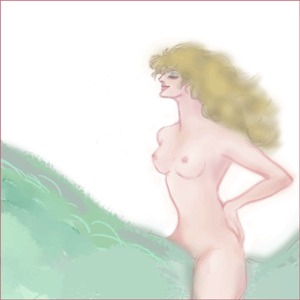
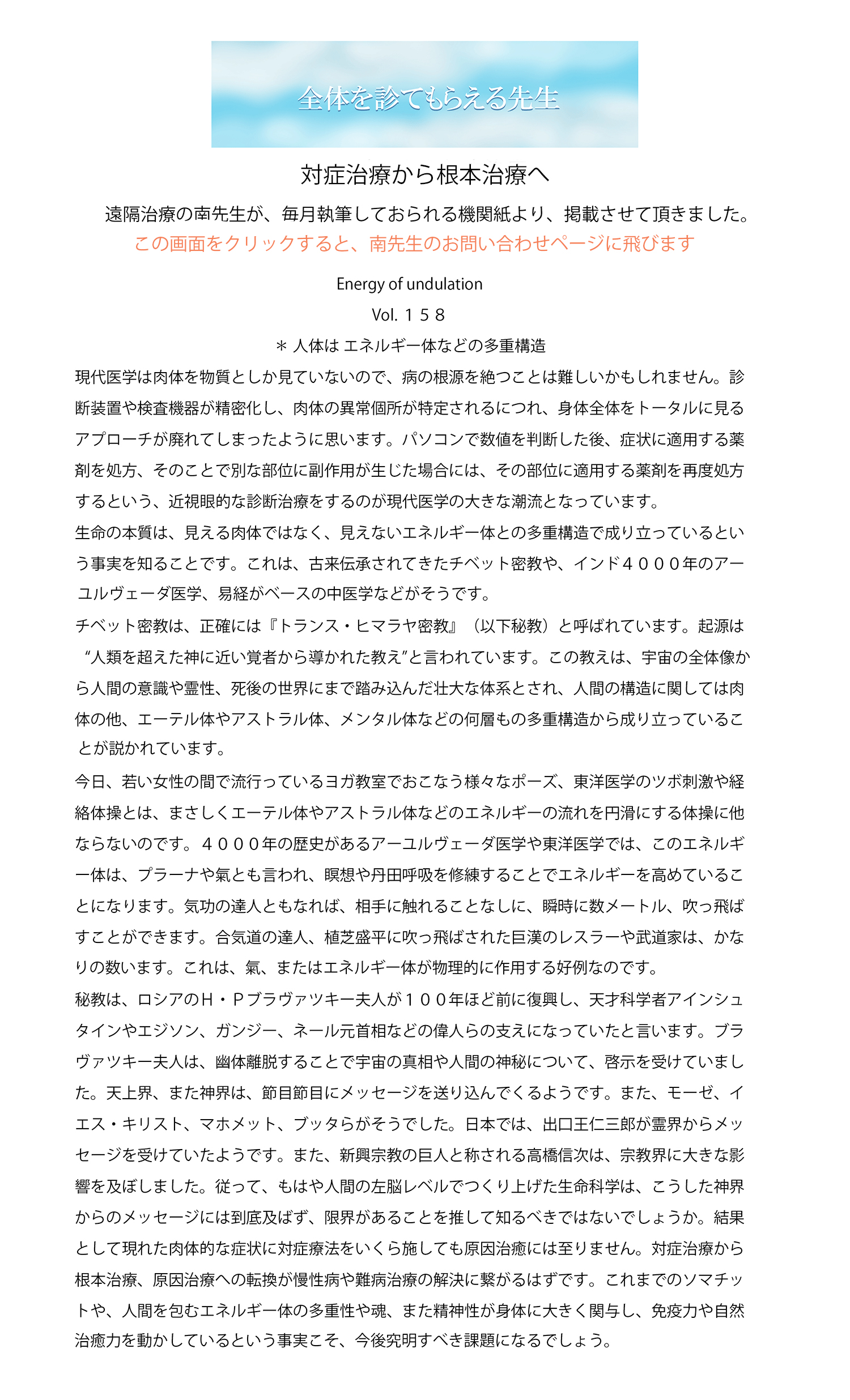
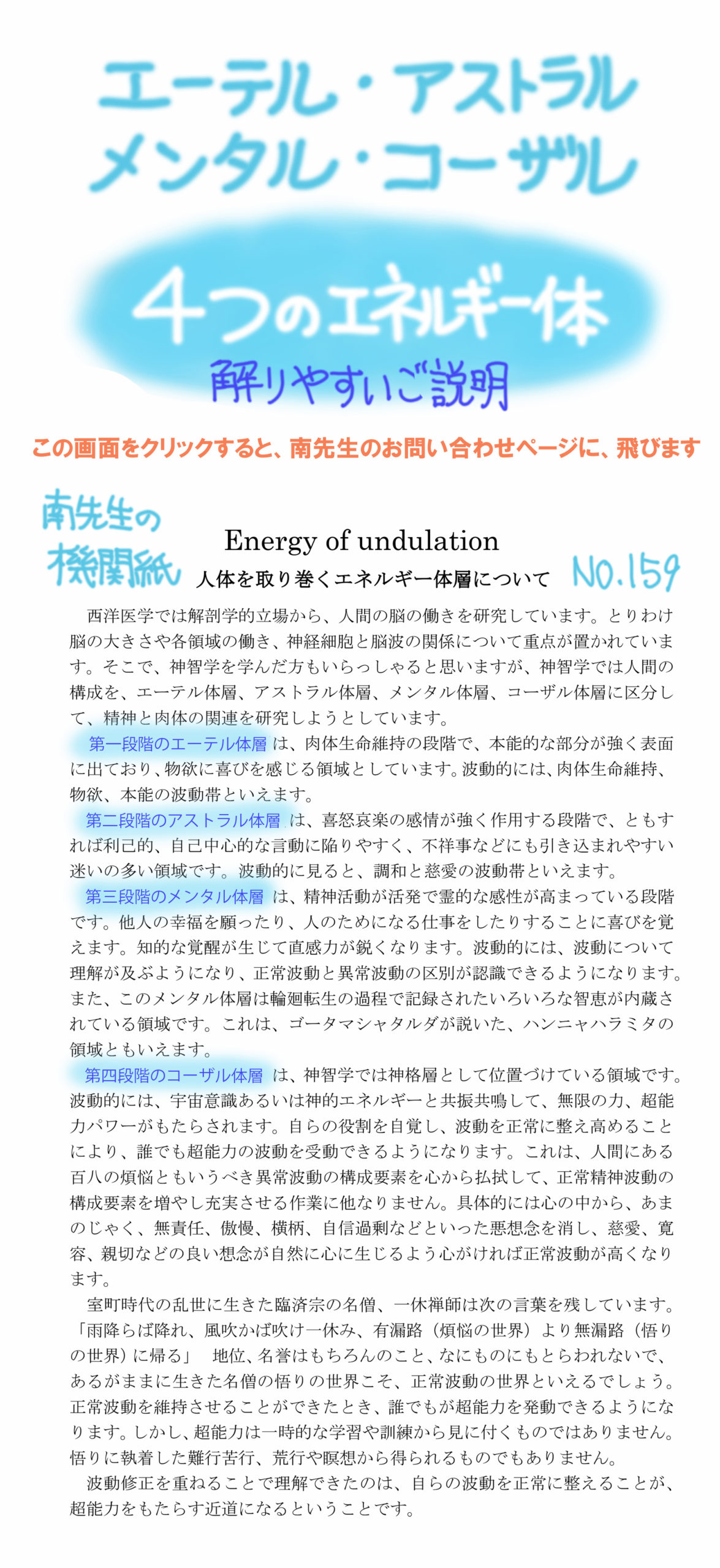





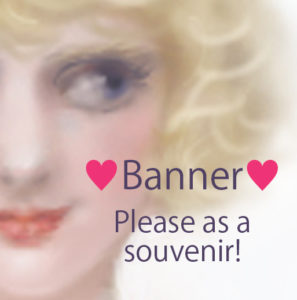

ミショーがベルギー生まれだったと知って、
またもやベルギーって感じでした。
シェーンベルグの「月に憑かれたピエロ」の歌詞の原詩も
アルベール・ジローというベルギーの詩人によるものだった。
いいもの見~つけた!って思うと、なぜかベルギーなのでした。