青年は全てを愛していた
 青年は全てを愛していた
青年は全てを愛していた
最近、どうして自分がビランになったのか? やっと判ってきた。ビランになる前の生活、それをすっかり変えなければならなかったから。
手が使えなくなる。これは文字通り完璧な禁じ手だった。封じ込んだのは、絵を描くこと。私はパステル画を描いていた。顔料を手指で紙にすり込むようにして描いてゆくパステル画は、重ねることで油絵のような重厚な描写ができる。そして人物の肌合いを、狙ったように出せるのが、自分にとってのパステルだった。独学なので、情熱で覚えたと自負していた。そして、その全てを止めた。
祖母が卒中に倒れ、母は何もできなくなり、私は二人の女性が旅立って行く姿を手放しで看ていた。描くことを忘れた自分は、もぬけの殻になったと思った。もちろん空になったのではなかった。それは芋虫が蛹に変態するように、今までの全てを作り替えるための序章だった。なぜなら、私の中には、愛があったから。
青年は全てを愛していた。うん、そうだ。自分もすべてを愛している。この一節を読んだとき、強くそう思ったのを覚えている。これはジュリアン・グリーンの小説「人みな夜にあって」の一節だ。この青年、ピストルで撃たれて死ぬんだけど、その瞬間がすごい!

背後から自分を撃った男から「このまま死なないでくれ!許すと言ってくれ!ただ一言でいい、Ouiと言ってくれ!」と、懇願されて「Oui」と、ささやく。自分を殺した相手を許せるのか? なぜ殺し、殺されるのか? そこには男同士の禁断の愛が隠されているからなんだけど、話の焦点はそこじゃない。殺されてもOuiと言える「許し」とは何か? 殺人という罪をも包み込む愛の大きさだ。青年は全てを愛していた。自分はこの人間の可能性に共感する。可能性の中に見えてくるのは和解だ。
和解、ビランとの和解、自分との和解、先祖たちとの和解、まだ見ぬ敵との和解。全てを包み込む愛の力、私はそれを信ずる。


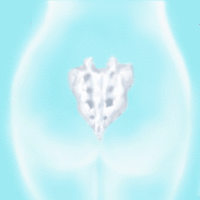




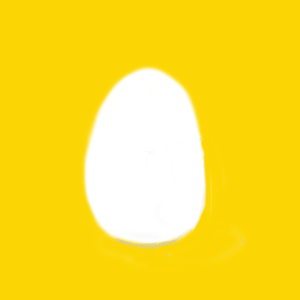
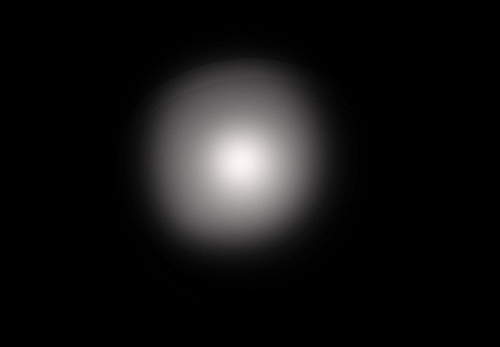
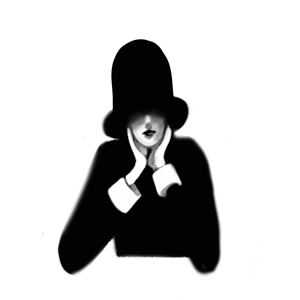

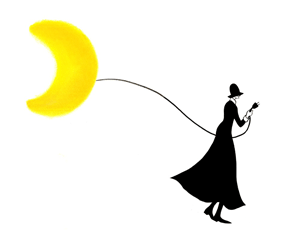
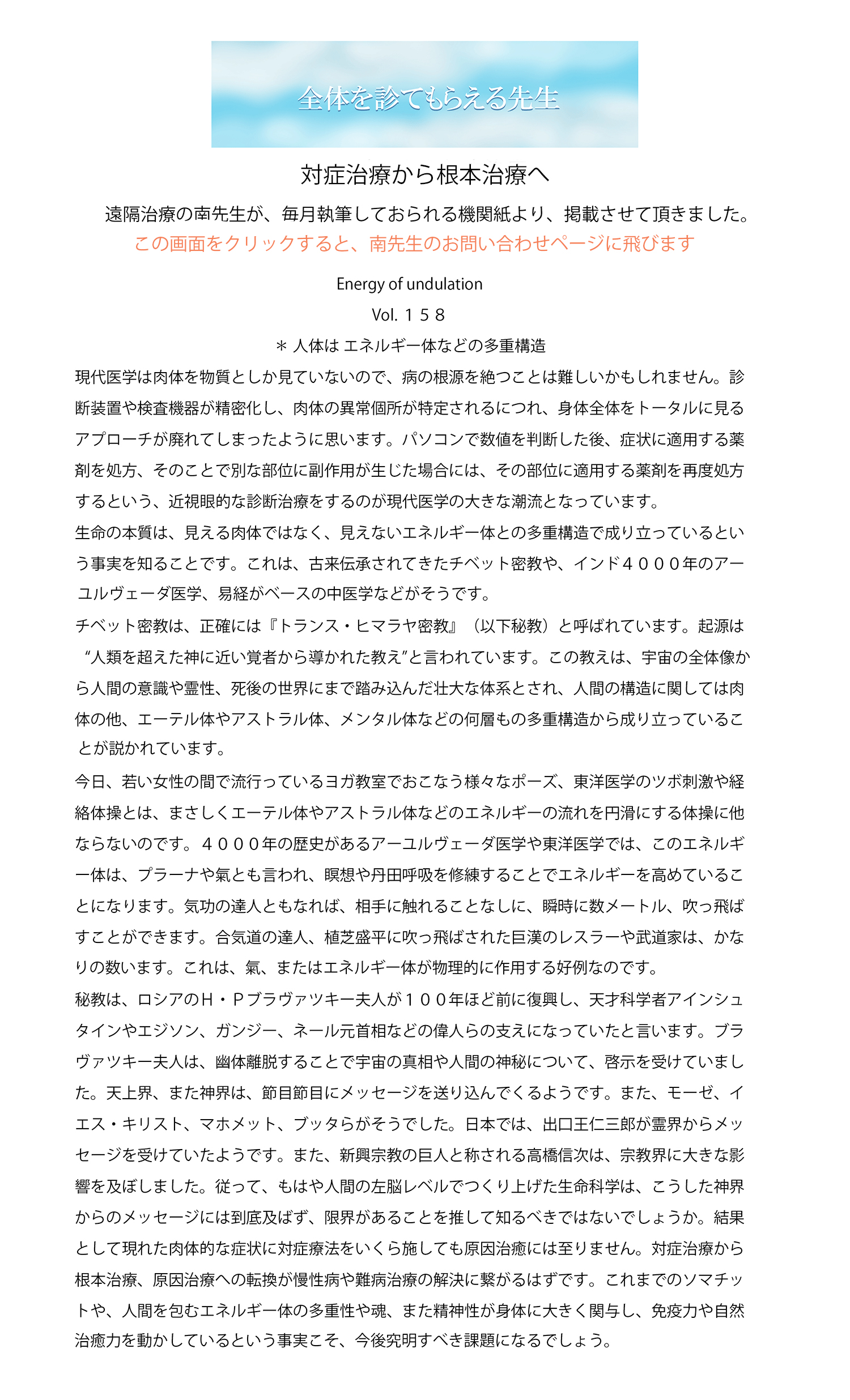
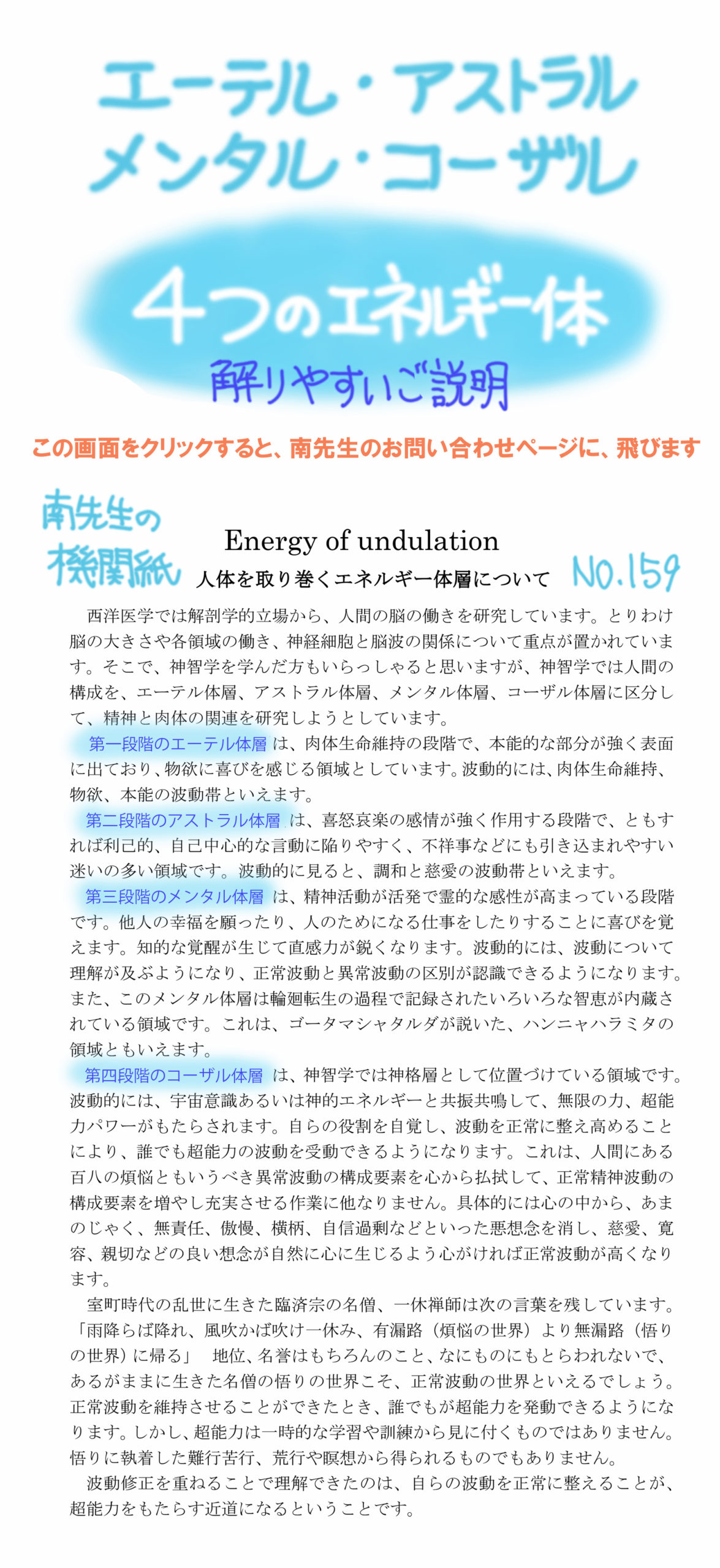





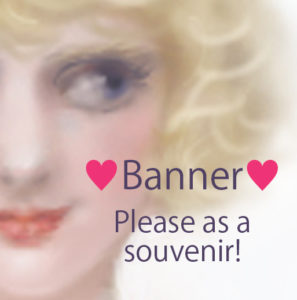

この記事へのコメントはありません。